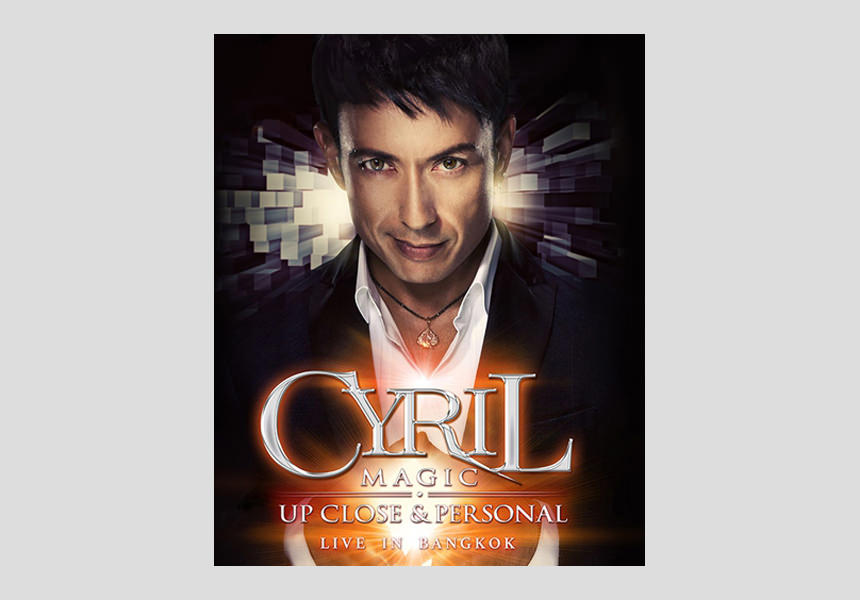アップス APE-SHIT
groschat produse vol.2
1998年4月23日(木)~26日(日)
阿佐谷/アルテパティオ
データ
groschat produse vol.2
アップス APE-SHIT
【原案】藤田洋
【作・演出】池谷なぎさ
【出演】藤田洋/鈴木隆/河崎耕士/美優樹/金森有基栄/日暮敏勝/池谷なぎさ/V・銀太
【日時】1998年4月23日(木)~26日(日)
4/23(木)-20:00
4/24(金)-20:00
4/25(土)-14:00/20:00
4/26(日)-14:00/17:00
※開場は開演30分前。当日券・整理券の発行は開演1時間前より行います。
【会場】阿佐谷/アルテパティオ
〒166-0001杉並区梅里2-40-19ワールドビルB1
[TEL]03-3316-5810
【チケット】[前売り・予約]2800円[当日]3000円(全席自由)
【前売・予約&問合せ】グローシャgroschat produce
【スタッフ】◎美術/V・銀太 ◎照明/清水利恭◎音響/青蔭佳代◎音響操作/TOMO◎劇中歌作曲/梅原ナオヤ
◎企画・製作/グローシャ◎協力/HAPPY/平川卓司/安江秀訓/ワカ
コピー
挨拶
◎挨拶◎

誰にも秘密の居場所がある。 それは映画館の一番前の席、もしくはデパートの屋上のベンチ、又は喫茶店でありBerであったりするだろう。これは、そんなどこかにあるはずの小さなBarの一夜のお伽話。そこでは、皆子供のようにはしゃぎ、遊びに熱中する。思い出せば、子供の頃の私たちにとって時間が経つのはなんて早かったことか。遊んでも遊んでも遊び足りず世界のすべてが遊びだった。大人になったからといえ、そう変わりないのではないか。今、私たちの遊びはロマンであると云い切れる。
「私を月に連れてって」女の甘い囁きが聞こえたらなんて素敵じゃないか。 役者を裏切り続けた40日間だったが、今度は私が彼らにしてやられる番だ。どきどきしすぎて私の心臓は爆発しちゃうかもしれない。でも、これ以上楽しいことを私は知らない。
では、一夜のロマンチックコメディをおなかいっぱいお楽しみください。
池谷なぎさ
物語り
◎物語り◎

雨の夜。その日男はついてなかった。何気なく乗ったタクシーに導かれ辿り着いたBar「WALK(ウォーク)」。
そこでは時の流れは空ろになり、如何わしい常連たちがそれぞれの人生(ストーリー)をでっち上げていた。橋の袂のストリッパー、ニューハンプシャーの七番。派手な背広の支配人。トイレに住み着く双子の姉妹たち……。場末のバーで繰り広げられる狂乱のセレナーデ(小夜曲)。男はカウンターの湯気の向こうに、もう一人の自分の人生を作り始めた。二時三十五分……。 女は来ない。
十年前の記憶が甦る。ボクはもう昔のボクじゃない。
深い闇の底に転げ落ちて行く男の前に、爽やかな朝は訪れるのだろうか。
「まったく酷い夜さ……教えてくれよきみは誰?」
甘い戦慄と苦いロマンスに埋め尽くされてぼくは身動きがとれないんだ…。
ひとクセもふたクセもある登場人物達が、可笑しくも残酷な夜を見せてくれることでしょう。
◎アップス=appetizer=ape-shit◎

アップスとは原案においてappetizerのスラングで前菜という意味だったが、スラング語辞典にそんな言葉は無く、やっと見つけたのが「ape-shit」だった。意味は「夢中になって、取り付かれて」などで、主に気が狂う、異常に興奮するといった具合に使われる。バナナをもらって興奮した猿がキャッキャッと騒ぎまくるといったイメージから出た表現らしい。原案は、アップスという言葉の響きにピンと閃いたと言うが、私は「ape-shit」に閃いた。
最初に原案を手にした折、妙に醒めた登場人物たちの空々しい会話が現代の若者を象徴していて、年代の開きを痛感させられた。彼らの美学はあまりにも内に秘められていて、他人との距離が計り知れない程遠すぎる。敢えて脚本では、人物達の名前を剥ぎ取り、「ついてない男」「ニューハンプシャーの七番」「派手な背広の支配人」等、それぞれの役柄を誇張せざる得ないように仕向けてみた。すなわち“そこにいるのは誰でもない、ただそういう役割を与えられただけの存在であるという戒めにも似た役者への挑戦だ。そこでいかに役者達が騙し合い刺激し合うことができるか、熱い物語の始まりである。
私たちはロマンを欲しがっているはずだ。
登場人物たちが、あわてふためき涙する姿は主観的に見ればシリアスだが、客観的に見ればコメディではないか。この作品をロマンチックコメディと呼ぶ理由はその辺にある。取りも直さず、役者が創り上げた人物像を超える偶然の一瞬を求めて、私たちはありとあらゆる必然を重ねていかなければならない。
最後にほくそ笑む事ができる観客達に嫉妬するのは私だけだろうか。
池谷なぎさ